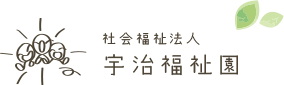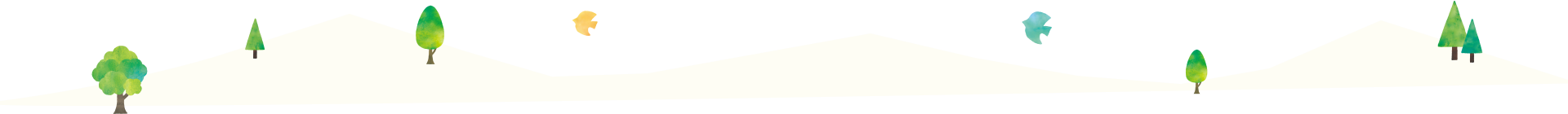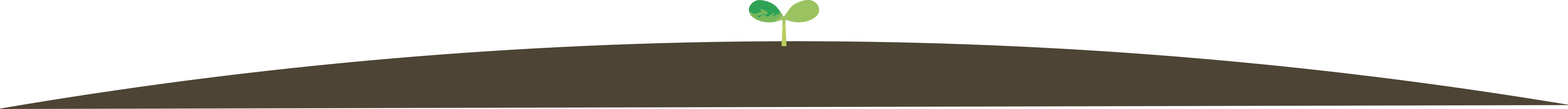「バケツ家の一族」のお話
理事長 すぎもと かずひさ
ダンゴムシさんを「見つけるというコト」があって、僕は動いた。彼を触りたい気持ちがムクムクして、トコトコ、トットコまっしぐら。親指と人差し指の間。ダンゴムシさんの確かな感触。丸めた手のひらの上で、そっと、指を開いた。つややかな背中の見事な屈伸技と白いお腹いっぱいの脚技でうじゃうじゃ語り掛けてくる。つんとするとコロン、ちゅんと摘まむとマルン。やりとりが愉しい。そんな掛け合いを楽しんでいくうちに、僕はダンゴムシさんに吸い込まれていく。
そこに、Aちゃんがやってきた。Aちゃんも何かに吸い込まれている顔だ。左手にバケツを持って、花壇の石をひっくり返していく。眼がすごい。口も尖ってくる。つぎの瞬間、カメレオンの舌のように右手がしなり、見事、ダンゴムシさんを捕まえたようだ。「ポトッ」。バケツの底の音がしたかと思うと、もうAちゃんの顔はバケツの中へ。そんなAちゃんに吸い込まれて、僕は、自分のダンゴムシをAちゃんが覗き込むバケツの淵でそっと放した。「ポトッ」。
Aちゃんが僕を見上げる。了解。二人の間が一気に溶けてAちゃんと僕は仲良くバケツを覗き込んだ。ダンゴムシさんがバケツのお家の中で、うじゃうじゃと手を振っている。態勢を変えるのが上手い。「ダンゴムシさん、友達呼んでくるね」、こんなふうにしてアリさんがやってくる。「ご飯もあげるからなぁ」、こんなふうにして丹精込めてちぎられた花びらやほかほかに滲んだ葉っぱが献上されていく。さらには、「小枝の寝床」に「小石の枕」、「泥団子のハンバーグ」など、どんどん意味づけられてはバケツのお家へ運ばれていく。連綿と起こり続ける「コト」の連綿の中で、出て来る事「デキゴト」が結ばれていく。 子どもを分かる、理解するとは、子ども達が繰り広げていく、これらの「デキゴト」に吸い込まれ、「我がコト」のように感じ、味わっていくことに他ならない。子どもは「デキゴト」を結ぶ一つ一つのコトの中で、全身を駆使し、知恵を絞り、ひらめき、身体的かつ精神的運動を増幅させていく。僕とダンゴムシさんの違いが僕の好奇心を生み新たな運動をつくっていく。僕とAちゃんの違いが二人に新たな運動をもたらし、仲間に広がっていく。石の特性が、土の特性が、生き物の特性が、一人一人の特性が、一つ残らず生かされて遊びの泉になる。子どもの活き活きとした生命感、躍動は、このように育まれていく。バケツ家の一族の根本に広がる環境、はてしない宇宙がある。