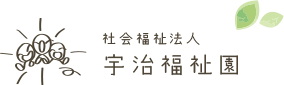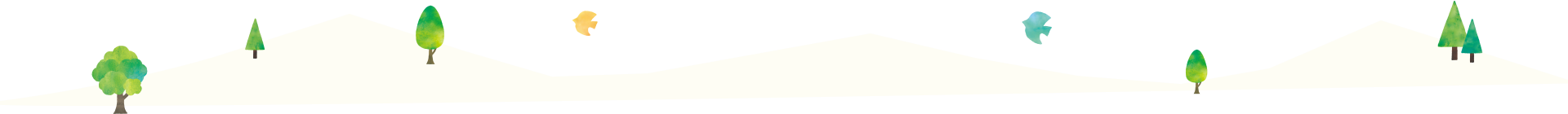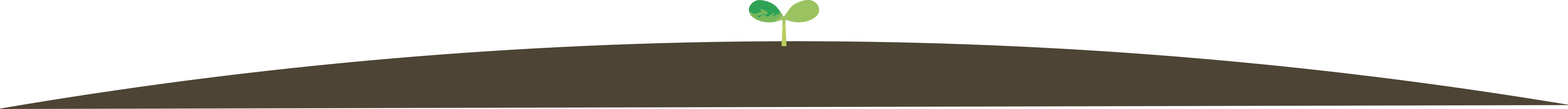『 素晴らしき生命のショートストーリー 』のお話
理事長 すぎもと かずひさ
僕は2歳。泣いていると先生がハルジオンの花をくれた。お母さんがしているキラキラの指輪のように薬指に乗せて僕の眼の前へ差し出したんだ。「どうぞ」と語り掛けてくれているような気がして嬉しかった。その喜びと先生の笑顔に甘えて、僕は先生の薬指にとまったハルジオンを摘まんで、じっと眺めた。ハルジオンも僕を見ている。眼差しが優しい。眼でお話しているうちに、なぜか、温かな気持ちが身体のすみずみへ浸み入ってきて、僕はいつしか泣き止んでいたんだ。
心淋しい感じが薄まってくるとあたりが気になってきた。広い園庭。突然、隣で遊ぶ同じクラスの3人の声が飛び込んできて、思わずその方へ振り向いた。すると、園庭の土にまみれた机を囲んでワイワイガヤガヤ何かやっている。僕はすっかり気になって近づいていった。
ダンゴムシだ。ダンゴムシにとってはアリーナのように広い机の上をコロコロ走っていく。ところで、机の端まで行って落っこちそうになると一人がクレーンのように手を伸ばし、ダンゴムシを持ち上げては、自分達の固めた泥団子の上でおろしたり、小石を並べたコースの上でおろしたりなど、環境によって変化する走りの様子を味わい、「生態」を学んでいく。3人のペースで迷走を繰り返すダンゴムシは彼らのヒーローである。食い入るように見つめる3人は、「僕」が加わり4人になった。泣いていたことなどとうの昔に忘れて、今を生きる「僕」の誕生である。
机の横には、ベンチがあった。ベンチは居心地の良さの象徴である。「ダンゴムシさんと一緒に座ろう」。仲間の一人がそう言い放ったと思ったら、あっという間に、1人、2人、3人とベンチに座っていく。ところが、あと一人がどうしても座れない。ダンゴムシさんを座らせようとするのだが、じっとしてくれないのだ。彼らの価値は「ダンゴムシさんと一緒にベンチに座ること」にある。行儀よく横並びに座る3人とその左端に空いたベンチのスペースでダンゴムシさんを座らせようと右往左往する1人と。じっとしたかと思うと動き出し、座らせる暇を与えてくれない。さっきとは逆にダンゴムシさんのペースに振り回されている。
それでもみんな幸せそうである。一緒に並んで座ることはできなかったけれど、その願いに向かって全身全霊を投じてきた充実感に満ちている。ハルジオンから始まった思いやりの連鎖。温かな思いを交換する素晴らしき生命のショートストーリー。